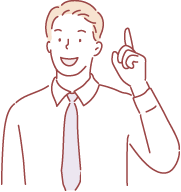省エネ計算は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)によって、申請や届出が義務付けられています。
近年、国全体として環境に配慮した取り組みが進められているため、将来的には省エネルギー計算の重要性が高まると予想されます。
しかし、省エネ計算は建築物の外皮性能やエネルギー消費量、さらに太陽光発電の有無などを総合的に判断する必要があるため、仕組みが非常に分かりにくいです。
本記事では、住宅の省エネ法やそれに基づく費用について詳しく解説しています。住宅における省エネ計算方法について知りたい方はぜひ参考にしてください。
住宅の省エネ計算なら「環境・省エネルギー計算センター」に相談しよう!
省エネ計算について迷ったら、累計3,000棟以上の省エネ計算実績を誇る「環境・省エネルギー計算センター」をご利用ください。
個人住宅から大規模な工場・商業施設まで、幅広い物件用途に対応しており、現在は年間1,000棟程度のサポートを行なっています。
徹底した価格調査により低価格での省エネ計算が可能で、お客様のリピート率は93%を超えています。
ただ安いだけでなく、早い納品対応と成果物の品質も保証しておりますので、初めての方も安心してお任せ下さい。
情報を社内で共有し、業務の効率化を図ることで、面倒で複雑な省エネ計算の負担を軽減します。
Webで24時間いつでもお問い合わせが可能なので、省エネ計算の代行を検討されている方はぜひご相談ください。
省エネ計算(建築物省エネ法)とは
省エネルギー計算とは、建物のエネルギー効率を示す計算手法です。
建物の大きさや使われ方に応じて、どれくらいのエネルギーが必要かという「基準値」が決まります。
その基準値と比べ、実際の建物設計で想定されるエネルギー消費量を計算し、省エネ性能を評価します。これにより、建物設計がエネルギー効率の観点から適切かどうかの判断が可能です。
他にも、省エネ計算は建築計画が省エネ計画であることを表すために、新築・増改築・空調設備などの改修・修繕・模様替えを行う際に使用されます。
また、住宅・非住宅の省エネ計算は、2017年4月1日施行の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、申請や届出が義務付けられました。
2025年4月からは、原則としてすべての新築建物に省エネ基準への適合が原則義務付けられたため、住宅業界全体で省エネ計算を実施する必要があります。
省エネ計算の計算式
住宅の省エネ計算は、「外皮計算」と「一次エネルギー消費量計算」の組み合わせで行われます。
外皮計算とは、壁、窓、屋根などの断熱性能を評価するためのものです。各部材の断熱性能(熱貫流率)とその面積を元に、全体の断熱性能を計算します。
住宅の一次エネルギー消費量の計算には、暖房、冷房、換気、照明、給湯など、住宅で消費されるエネルギーの全てが含まれます。この計算は、各設備の性能や使用時間、家族構成などに基づいて行います。
これらの計算結果を法律で定められた基準値と比較します。具体的な計算式は以下の通りです。
[BEI=設計一次エネルギー ÷ 消費量基準一次エネルギー消費量]
※BEI=一次エネルギー消費性能
設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下で、かつ外皮性能が基準値を満たしている場合、その住宅は省エネ基準に適合しているとされます。
このように、省エネ計算は住宅の設計段階で行われ、その結果に基づいて設計が改善されることもあります。最終的な目的は、エネルギー消費を抑え、環境負荷を減らすことです。
住宅の省エネ計算の特徴とは
住宅の省エネ計算は、2017年以前であれば一次エネルギー消費量(BEI値)のみが評価対象でした。
しかし現在では、一次エネルギー消費量(BEI値)と外皮性能であるUA値(外皮平均熱貫流率)および、ηAC値(冷房機の平均日射熱取得率)の全ての基準を満たす必要があります。
一次エネルギー消費量基準は、住宅のエネルギー消費を評価する主要な基準の一つで、その目標は設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下になること、すなわちBEI値が1.0以下になることです。
UA値とηAC値は、住宅のエネルギー効率を測定するための数値です。これらの数値は、住宅の省エネ性能を明確に示すために使用されます。
これらの値が基準を満たすことは、住宅が適切に設計され、エネルギー効率が高いことを示しています。
住宅の省エネ計算によって、建物のエネルギー効率の理解、及び改善する道筋を立てることが可能です。
3つの住宅の省エネ計算の方法
省エネルギー基準の評価は、建築物省エネ法に基づき、「外皮性能」と「一次エネルギー消費性能」の2つの観点で行われます。
この評価を進めるには、以下の2つの手法が用意されています。
- 標準計算ルート
- 仕様ルート
「標準計算ルート」を用いると、外皮面積を精密に計算することで、省エネルギー基準の評価を高精度に行うことが可能となります。
「仕様ルート」に関しては以下の記事をご参考ください。
省エネ計算を簡易にする仕様基準とは?概要やメリット、使い方を解説
住宅の省エネ計算の対象
2025年4月以降、省エネ計算の対象になるのは、原則としてすべての新築される住宅です。
住宅の省エネ計算プログラム
住宅の省エネ計算を行う無料ソフトの中で、特におすすめなのは「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」です。
住宅用の計算プログラムは、総合的な住宅の消費エネルギー性能を計算できるだけではなく、窓や外壁など建物外皮の性能を計算することも可能です。
地域ごとの気候特性に対応した計算プログラムもあるため、住宅を建てる地域に合わせた計算ができます。
また、戸建住宅だけではなく集合住宅用の計算ソフトも揃っているので、マンションやアパートの消費エネルギー消費性能の計算も可能です。
【補足】非住宅の省エネ計算について
住宅と非住宅で省エネルギー計算の方法はいくつか異なる点があります。
具体的には、評価の対象や計算手法などです。
例えば、住宅の省エネルギー計算では、主に住宅の外皮性能と冷房機の平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量(BEI値)を評価します。
一方、非住宅では、建築物全体のエネルギー消費性能を評価するため、冷暖房負荷、照明負荷、換気負荷、給湯負荷、エレベーター負荷などを含む一次エネルギー消費量を評価します。
また、非住宅の評価方法は、「標準入力法」「モデル建物法」「モデル建物法(小規模版)」の3つがあります。
非住宅の省エネ計算について、より詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
非住宅の省エネ計算とは?3つの評価方法の違いや一次エネルギー消費基準の考え方について、専門家が徹底解説
住宅の省エネ計算にかかる費用
専門家による省エネ計算の費用は、数万円から十数万円程度です。
省エネ計算の費用は、住宅の規模や設計の詳細、業者の専門性などにより異なります。
具体的な費用は、依頼する会社や業者によっても大きく異なるため、いくつかの業者から見積もりを取ることがおすすめです。
省エネ計算に投じる初期費用は、エネルギーコストの削減や、快適な住環境の実現につながります。そのため、住宅の省エネ計算の費用を理解し、計画的に進めることが重要です。
省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。
累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。
※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。