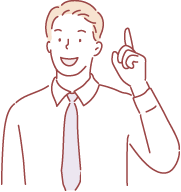長く良好な状態で暮らせる住宅のために、必要な措置を講じた「長期優良住宅」。
2022年度の長期優良住宅法改正と2025年度の基準改定により、耐震性の認定基準が見直されました。
この記事では、長期優良住宅の新基準や耐震等級3を取得するメリット、耐震等級の計算方法について解説します。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長く良好な状態で住み続けられるための措置が施された良質な住宅です。
優良な住宅建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づいて実施することで、認定を受けられます。
長期優良住宅を建てる際に重視する性能は次の10項目です。
| 性能項目 | 条件 |
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使い続けられる |
| 耐震性 | 大地震後の損傷レベルの低減と、継続利用のための改修の容易化を目指す |
| 省エネルギー性 | 省エネに必要な断熱性等を確保 |
| 維持管理、更新の容易性 | 耐用年数が低い設備の維持管理を容易に行うための措置が講じられている |
| 可変性 | 住む人のライフスタイル等の変化に合わせて間取りの変更が可能な措置が講じられている |
| バリアフリー性 | バリアフリー改修に対応できるスペースを確保 |
| 居住環境 | 地域における居住環境の維持及び向上に配慮 |
| 住戸面積 | 住みやすい居住水準を確保するための床面積の確保 |
| 維持保全計画 | 将来必要になる定期的な点検・補修等に関する計画を策定 |
| 災害配慮 | 自然災害による被害の防止や軽減に配慮 |
2022年10月施行!長期優良住宅の認定基準改正ポイント4点
近年、持続可能な社会づくりのために、省エネ性能の高い住宅の普及が推進されています。
長期優良住宅も省エネ性能の高いZEH水準レベルが求められるようになり、2022年10月には長期優良住宅の普及に関する法律が改正されました。
ここでは、長期優良住宅で知っておくべき新基準について4つ解説します。
断熱性能等級を4から5へ
前述したとおり、長期優良住宅の省エネ性能をZEH水準に合わせるため、断熱性能等級が4から5に引き上げられました。
断熱性能等級5は、長期優良住宅の普及に関する法律が改正されたのと同年に新設された等級で、ZEH水準に相当する、より高いレベルの断熱性能が求められる基準です。
一次エネルギー消費性能の認定基準を導入
従来の長期優良住宅の省エネ性能は断熱性能のみが対象でしたが、新たに一次エネルギー消費性能の基準が設けられました。
断熱性能等級と同様に、ZEH水準レベルである一次エネルギー消費量等級6のクリアが条件です。
既存住宅認定制度の新設
従来の規定では新築や増改築時が長期優良住宅制度対象でしたが、建築行為を行わない既存住宅でも認定できる制度が新設されました。
良質な既存住宅を長期優良住宅として認定するのが目的で、建築行為を伴う住宅と同様に住宅ローンの金利引き下げや税の特例措置などの恩恵を受けられます。
耐震等級の見直し(2025年度改正)
改正前は「壁量計算または許容応力度計算で耐震等級2以上」の取得が基準でしたが、2022年の改正後は「壁量計算を用いる場合は耐震等級3」に引き上げられました。
ただし2025年4月の基準改定により、耐震等級の条件は「壁量計算または許容応力度計算
で耐震等級2以上」と見直されました。
2022年に耐震等級を3へ引き上げたのは、ZEH水準に対応した構造安全性を確保するためです。
しかし、住宅性能表示制度の見直しで壁量計算がより実態に合った方法に改正されたため、2025年4月以降の壁量基準で計算した場合は耐震等級2でも可能となりました。
ここからは長期優良住宅に必要な耐震等級の概要や、壁量計算・許容応力度計算など計算方法について解説します。
耐震等級とは
耐震等級とは、地震に対する建築物の倒壊・損傷しにくさを3つのレベルに分けて表した指標です。
2000年に施行した品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく「住宅性能表示制度」の評価項目のひとつで、専門知識のない消費者にも建築物の耐震性をわかりやすく示すために定められました。
等級は1〜3で、それぞれの基準は次のとおりです。
| 耐震等級 | 認定基準 |
| 1 | 建築基準法で定められた最低基準で、震度6~7相当の地震で倒壊・崩壊しないレベル |
| 2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震性で、災害時の避難場所となる学校などの公共施設と同レベル |
| 3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性で、災害時の復興拠点となる警察署や消防署と同レベル。 |
現在の建築基準法で建てられた新築住宅は、最低でも耐震等級1の耐震性が備わっています。
前述したとおり長期優良住宅の場合、令和7年度以降の壁量基準で計算すれば耐震等級2クリア可能です。
それでも最高ランクである耐震等級3を取得することで得られるメリットと、注意点を解説します。
耐震等級3を取得するメリット
耐震等級3を取得する最大のメリットは、災害後も住宅で生活を継続できる可能性が高い点です。
耐震等級1でも大地震で倒壊・崩壊しませんが、損傷は避けられません。
大きな損傷が発生した場合、建て替えが必要になる恐れもあります。
一方耐震等級3の住宅は、2016年に発生した最大震度7の熊本地震で、9割近くの住宅が無被害でした。
災害時だけでなく災害後の生活を守るためにも、耐震等級3の耐震性は魅力的です。
参照:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書のポイント」
また、地震保険は住宅の耐震に応じて割引が受けられますが、耐震等級が高いほど割引率が高くなります。
耐震等級3を取得する際の注意点
耐震等級3を取得する際に気を付けたいポイントは初期コストの高さです。
通常の設計費用にプラスして耐震等級3の基準を満たしているのを証明する構造計算や、施工費用などで、耐震等級1の住宅よりも200万近い費用がかかる場合があります。
初期費用を抑えるために、「子育てグリーン住宅支援事業」など国や地方自治体が支援する補助金制度を積極的に活用することも検討する必要があります。
長期優良住宅の耐震等級の計算方法
耐震等級の算出には主に3つの計算方法があります。
それぞれの計算方法の特徴について、詳しく解説します。
建築基準法の仕様規定による壁量計算
仕様規定による壁量計算は、建築基準法で決められた仕様で住宅を設計し、壁量計算・N値計算・四分割法など簡易的な計算方法で耐震等級を算出する方法です。
最低限の計算で済むため設計者の負担が少なく、時間やコストを削減できるのも利点です。
しかし、建築基準法を最低限満たすためだけの計算方法なので、耐震等級1までしか保証できません。
この計算で耐震等級2以上をうたう建築物は、公的に認められた等級でないため注意しましょう。
品確法の性能表示による壁量計算
品確法の性能表示に基づいた壁量計算は、仕様規定の項目にプラスして、接合部の強度や床・屋根倍率など細かな構造計算も行います。
住宅の品質を確保するため性能を数値化して評価し、構造全体のバランスを考慮しながら耐震性が検証されます。
性能表示計算で設計した住宅は、耐震等級2以上の認定を受けられます。
建築基準法の許容応力度計算
許容応力度計算とは、柱や梁など住宅を構成する材料すべてを計算するため、耐震性を計算する方法のなかでもっとも信頼性の高いものです。
耐力壁の必要量も増えるため、最高レベルの耐震性も期待できます。
壁量計算と許容応力度計算の耐震等級は同じレベル?
壁量計算と許容応力度計算の耐震等級は、同じ等級でもレベルが違います。
詳細な構造計算を行う許容応力度計算の方が、より耐震性や信頼性が高いのが特徴です。
品確法の性能表示による壁量計算でも、許容応力度計算でも耐震等級2以上なら長期優良住宅を取得できますが、確実に耐震性を確保するなら許容応力度計算がおすすめです。
長期優良住宅の耐震等級でよくある質問3選
長期優良住宅の耐震等級でよくある質問を3つ解説します。
長期優良住宅は地震保険料の割引が受けられる?
地震保険料の割引は、住宅の耐震等級や免震性などによって適用されます。
耐震等級は高いほど割引率も大きく、耐震等級3の場合、最大50%の割引を適用する保険会社もあるようです。
長期優良住宅は耐震等級2以上を認定基準にしているので、地震保険料の割引を受けられます。
耐震等級3と耐震等級3相当の違いは?
耐震等級3と耐震等級3相当の違いは、公的に認められているかどうかです。
耐震等級3は住宅性能評価機関に申請して性能を検査し、クリアした場合のみ取得できます。
一方、耐震等級3相当はその建築物を設計した建築会社等の評価で、正式な認定ではありません。
実際の耐震性能は建築会社しか把握していないので、信憑性が低いといえます。
耐震等級3の認定を受けることで利用できる、地震保険料割引などの優遇措置も対象外です。
長期優良住宅で耐震等級を証明できる?
地震保険割引の適用を受けるためには、耐震等級を証明できる書類が必要です。
長期優良住宅が耐震等級を証明する場合は、長期優良住宅認定の際に品確法に基づいて登録住宅性能評価機関が作成した、「技術的審査適合証」もしくは「長期使用構造等である旨の確認書」が証明書として利用可能なケースが多いようです。
まとめ
2022年に長期優良住宅制度の改正で、省エネ性能がZEH水準に引き上げられたのに伴い、ZEH水準の構造躯体に耐えられる耐震性として、暫定的に「壁量計算で耐震等級3以上」が認定基準になりました。
しかし、2025年に壁量計算がより実態に適した方法へ見直されたため、壁量計算でも耐震等級2の安全性が担保可能になり、暫定的な「耐震等級3」は廃止されました。
今後も省エネ水準の引き上げによって、求められる耐震性も左右される可能性があるため、最新情報を随時チェックするのが大切です。
省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。
累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。
※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。