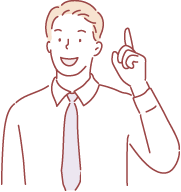住宅性能評価は、国が定める住宅性能の基準を満たすことで取得することができます。
本記事では、住宅性能評価を事業者が取得するメリットを紹介します。
また、住宅性能評価を取得する際のデメリットについても解説しているので、住宅性能評価の取得を検討している方はぜひ参考にしてください。
住宅性能評価とは
住宅性能評価とは、国が定めた住宅評価基準に基づき住宅の性能を評価する制度です。
新築の住宅性能評価は、性能の表示項目として10分野33項目に区分して評価します。
住宅品質確保法に基づいて、国土交通省に登録された第三機関により住宅の性能評価が行われ、一定の基準を満たすことで住宅性能評価書が交付されます。
また、住宅性能評価では住宅の性能に応じて等級が与えられ、等級の数値が高い建物ほど高性能の住宅であることを示します。
事業者が住宅性能評価を取得するメリット
住宅性能評価を取得するメリットは主に以下の5つがあります。
- 住宅性能が可視化され、入居者へアピールできる
- 資産価値が高くなる可能性がある
- 紛争の解決がしやすくなる可能性がある
- 地震保険料の割引を受けられる
- 住宅ローンの金利を引き下げることができる
住宅性能評価の取得を検討している事業者は参考にしてください。
住宅性能が可視化され、入居者へアピールできる
住宅性能評価では統一された評価基準をもとに住宅の性能を評価しているため、住宅に関する知識が少ない方でも客観的に住宅の性能を比較できます。
そのため、住宅性能評価を取得して高い評価を受けた住宅は、性能の良さをアピールできるので、入居者から選ばれやすくなります。
住宅の性能が可視化され、入居者に分かりやすくアピールできる点がメリットです。
資産価値が高くなる可能性がある
住宅性能評価を取得した住宅は、国が定めた一定の基準をクリアした建物であることの証明になります。
住宅性能評価を取得した住宅は劣化対策や建物の維持のしやすさなどの対策がされているので、住宅の品質を維持しやすく将来的に高い価格で売却することができます。
また、住宅性能評価を取得したアパートやマンションは性能の高い住宅であることをアピールできるので、高い賃料で契約が取りやすくなります。
紛争の解決がしやすくなる可能性がある
住宅性能評価を取得した住宅は、トラブルが発生した際に指定住宅紛争処理機関へ紛争処理の申請ができます。
指定住宅紛争処理機関とは、国土交通大臣が指定する各地域の弁護士会のことです。
弁護士に紛争の処理を依頼できるため、個人で対応するよりトラブルの解決が早くなります。
紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する全ての紛争の処理を依頼できます。
地震保険料の割引を受けられる
住宅性能評価を取得した住宅は火災保険などの特約として付く地震保険料の割引が受けられます。
地震保険料の割引額は、住宅性能評価で取得した等級により異なります。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の割引率は以下の表です。
【地震保険料の割引率】
| 耐震等級割引 | 耐震等級3 | 50% |
| 耐震等級2 | 30% | |
| 耐震等級1 | 10% |
最高等級の3等級を取得すると、最大50%の地震保険料が割引になります。
このように住宅性能評価を取得することで、地震保険料の大幅な割引を受けることができます。
出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「制度のメリット」
住宅ローンの金利引き下げがある
住宅性能評価を取得することで、住宅ローンの金利の引き下げが受けられます。
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している、長期固定金利住宅ローン制度の「フラット35S」の利用が可能です。
住宅性能評価の取得により住宅購入時のローンの金利を抑えられることもメリットです。
また、事業者は住宅ローン控除を受けられる住宅であることをアピールできるので、より入居者の目にとまりやすくなります。
新築の住宅性能評価の取得についてお困りなら、「環境・省エネルギー計算センター」へ問い合わせしよう!
新築の住宅性能評価の項目・等級についてお困りの方は、「環境・省エネルギー計算センター」をご利用ください。
これまでに、個人住宅、小規模事務所、大型工場など累計2,600棟以上の建物をサポートしており、豊富な実績があります。
また、当社では新築の設計住宅性能評価を取得するための申請書作成代行を行っています。
新築の設計住宅性能評価についての不明点は、ぜひ当社までお問い合わせください。
※補助金の詳細に関しましては管轄している事務局や行政庁にご確認ください。
※竣工済みの新築住宅や既存住宅は現況検査が必要となりますので、評価機関に直接ご相談ください。
住宅性能評価を取得するデメリット
住宅性能評価は取得することで多くのメリットが得られる反面、デメリットもあるため注意が必要です。
住宅性能評価を取得する主なデメリットには、以下の4つがあります。
- 建築コストが上がる
- 取得費用がかかる
- 相反する項目がある
- 設計デザインが制限される可能性がある
住宅性能評価はメリットだけでなくデメリットも考慮して取得を検討しましょう。
建築コストが上がる
住宅性能評価を取得するためには、通常の建築費に加えて追加のコストがかかる場合があります。
住宅性能評価は、より高性能な住宅であるほど高い等級が取得できます。
住宅性能評価でより良い評価を受けるためには、性能の高い資材の使用や技術力の高い会社・職人への依頼が必要です。
性能の高い資材の使用や技術力の高い会社・職人への依頼をする場合は、通常の建築と比べて追加のコストがかかります。
住宅性能評価で良い評価を受けるためには、追加の建築コストが必要になる場合があるので検討が必要です。
取得費用がかかる
住宅性能評価を取得するためには、取得費用が必要です。
住宅性能評価には、住宅建設時の設計図書の段階を評価する「設計住宅性能評価」と住宅の施工段階と完成段階を審査する「建設住宅性能評価」の2種類があります。
設計住宅性能評価のみを取得する場合は10万円程度、2種類とも取得する場合は20万円程度の取得費用が必要です。
住宅性能評価の取得には費用がかかる点もデメリットです。
相反する項目がある
住宅性能評価には相反する評価項目があります。
例えば、室内に多くの光を取り込めるように窓を大きくすると耐震評価が下がります。このようにある評価項目を良くすると別の評価項目が悪くなるケースがあります。
そのため、間取りや周辺環境、ライフスタイルによって必要な等級レベルを判断して建築するのがおすすめです。
相反する項目があるため、全ての項目で高い等級を取得できるとは限らないので、注意してください。
設計デザインが制限される可能性がある
住宅性能評価を意識しすぎると、建築時に設計デザインが制限される可能性があります。
耐震性を上げるためには窓の大きさに制限があるなど評価項目を意識すると、住宅購入者が思い描く理想の住宅の建築が難しくなります。
住宅購入者の意見や住宅性能評価のバランスを考えた設計デザインが必要です。
新築の住宅性能評価の取得を検討しているなら「環境・省エネルギー計算センター」に相談しよう!
新築の住宅性能評価の取得を検討している方は、「環境・省エネルギー計算センター」をご利用ください。
当社では新築の設計住宅性能評価の申請書作成代行業務を行っております。
新築の住宅性能評価の手続きに悩みを抱えている方は、ぜひ当社へお問合せください。
※竣工済みの新築住宅や既存住宅は現況検査が必要となりますので、評価機関に直接ご相談ください。
※補助金の詳細に関しましては管轄している事務局や行政庁にご確認ください。
このコラムに関して詳細を確認したい場合や、省エネ計算届出に関しての質問などはお気軽にお問い合わせください。
※個人の方はまずは身近な設計事務所や施工会社にご相談された方が手続きがスムーズです。